最終更新 2023.2.24
ようこそ(^^)/
人生を豊かに生きるためには、健康とお金がとても大切と考える当サイトの管理人ぱんぱんぱぱです。
さて、みなさんは確定申告の手続きは終了しましたか?

管理人は昨日税務署に赴き、手続きを済ませてきました。

はい、確定申告のIT化は年々進化し、今や自宅や外出先で、e-TAXやスマホで手続きができる時代です。
ですが、管理人は頑なに税務署で確定申告を行っています。

一言に確定申告といっても、しっかりと準備しておかないと、もらえるはずの還付金が手に入らなくなることもあります。
特にサラリーマン(給与所得者)は、確定申告の対象となる項目は少ないです。
それでも、確定申告しないと払いすぎた税金を取り戻すことはできません。
しっかりと準備して、確定申告にチャレンジして損はありません!
- 1 わが国の国民負担率は超重税である真実
- 2 サラリーマンができる確定申告はたかが知れている
- 3 給与所得控除できるものは?
- 4 小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)が2022年5月より改正!
- 5 医療費駆除も超簡単に!
- 6 我が家の令和4年分確定申告 夫編
- 7 我が家の令和4年確定申告 妻編
- 8 まとめ
1 わが国の国民負担率は超重税である真実
わが国で暮らす限り、国民には納税の義務があります。
納税することによって、国や地方が税金を使って、私たち国民を安全に安心して生活できるように守ってくれます。
しかし、年々、国民負担率は上昇しています。
国民負担率とは、租税負担及び社会保障負担を合わせた義務的な公的負担の国民所得に対する比率のことです。

令和4年
租税負担率 27.8%
社会保障負担率 18.7%
計 46.5%
ざっと、収入の半分近くが税金や社会保障負担(年金、健康保険、介護保険等)で消えています。
収入が増えない中、記録的なインフレで物価が騰がっています。
可処分所得が目減りし、暮らしがきびしくなっています。
これに加えて、突然の子育て世代への手厚い社会保障施策が、財源もないのに始まろうとしています。
将来年に10兆円という構想まで飛び出しています。
国家予算の1割を子育て支援施策に回せば、さらに1割もの負担が増えてしまいかねません。
確定申告で少しでも払いすぎた税金を取り戻しましょう!
2 サラリーマンができる確定申告はたかが知れている
サラリーマン(給与所得者)の確定申告は、人生のイベントを除けば所得税に関するものがほとんどです。
所得税は、所得税法で10区分に分類されています。
給与所得
事業所得
利子所得
配当所得
譲渡所得
不動産所得
一時所得
退職所得
山林所得
雑所得
サラリーマン(給与所得者)が確定申告を行うのは、主に給与所得から対象となる所得控除を行い、給与所得で源泉徴収された所得税額のうち控除できる所得税額を還付するのが目的です。
3 給与所得控除できるものは?
給与所得控除できる項目はたかが知れています。
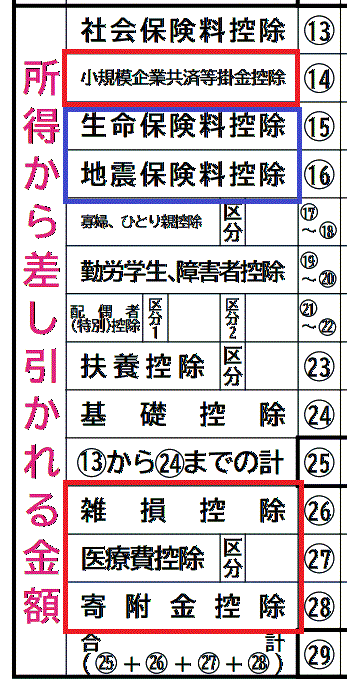
サラリーマンの場合、生命保険料や地震保険料は会社側が年末調整を行ってくれるので、追加しない場合は確定申告は不要です。
また、小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)は、年末調整でも可能ですが、掛金額を会社側に把握されるのが嫌な人は、確定申告で手続きすることができます。
管理人は会社側に覗かれるのが嫌なので、年末調整では申請しないで確定申告を行っています。
この他にも、特別控除や税額控除ができる項目もあります。
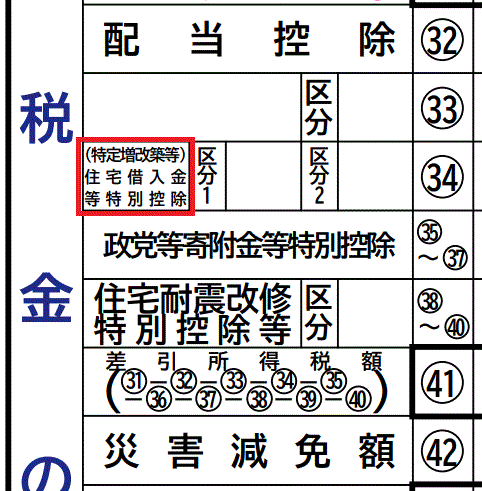
サラリーマンの確定申告は主に次の物が対象となります。
1 小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)
2 雑損控除
3 医療費控除
4 寄付金控除(ふるさと納税)
5 住宅借入金等特別控除
このうち、雑損控除は地震や台風などで被害を受け修理等に要した控除、住宅借入金特別控除はマイホームを購入した際のローンに対する所得税控除で、最初の1回目だけ確定申告が必要となります。
サラリーマン(給与所得者)が、毎年確定申告できる項目は次の3つとなります。
1 小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)
2 医療費控除
3 寄付金控除(ふるさと納税)
対象となる項目を積極的に活用しないと給与所得からの控除額は年末調整だけとなります。
ふるさと納税による寄付を行った場合は、必ず確定申告を行う必要があります。
なお、ふるさと納税は、5つ以下の自治体に寄付した場合は、ノンストップ特例制度により、寄附した自治体に1月10日までに手続きを取れば、確定申告を行わなくとも寄付した自治体が代行して確定申告手続きを行ってくれます。
4 小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)が2022年5月より改正!
iDeCoは、2021年度まで59歳までの人が対象でした。
3年前に満期定年退職した管理人は、現職時代iDeCoの手続きが面倒くさく、期間も短かったので、ついに手続きをしないで卒業してしまい、iDeCoの節税効果にはありつけませんでした。

ところが、老齢人口の増加に伴い、2022年5月より、iDeCoの対象年齢が拡大となりました。

有識者によるiDeCoのコラム#9 法改正でますます拡充2023年からiDeCoはどう変わる?|有識者によるiDeCoのコラム|iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)【公式】
管理人もこの改正により、ついにiDeCoの恩恵に授かることができました!
感無量です!

iDeCoは、掛け金分がそっくり給与所得から控除できます。
たとえば月20,000円を掛金とした所得税課税率20%のサラリーマンの場合です。
240,000円×20%=48,000円が確定申告でまるまる還付されます。
これほどお得な制度はありません!
元本目減りが怖ければ、銀行定期預金をiDeCo運用の対象とすれば、元本が保証されます。
若いうちに加入すればするだけお得です。
なお、iDeCoは今後70歳まで延長されることになっています。
5 医療費駆除も超簡単に!
医療費控除は、年間10万円以上医療費がかかった場合、確定申告することにより、10万円を引いた額の残りが所得控除の対象となります。

医療費控除はこれまでは本当に面倒でした。
領収書をしっかりと保管し、年間計算を行わなければなりませんでした。
しかし、平成29年分から領収書の添付は不要となり、医療費明細書を添付することとなりました。
しかも、協会けんぽなど自身が加入している健康保険組合の医療通知書を添付すれば、医療明細書の入力もトータルで済むようになりました。
これが超便利で超楽です。
ただし、医療通知書は1-9月末(10月末)までのものなので、通知書発行後に通院した場合は、領収書を保管し、医療費明細書に入力する必要があります。
また、セルフメディケーション制度で確定申告する場合は、どちらか一方の医療費控除しか使えないので、注意が必要です。
また、医療費控除は同居する家族単位での確定申告が可能です。
6 我が家の令和4年分確定申告 夫編
以上を踏まえ、ふるさと納税寄付先の自治体からの寄付金納税証明書を揃えての確定申告を行いました。
管理人の還付金(予定額)です。
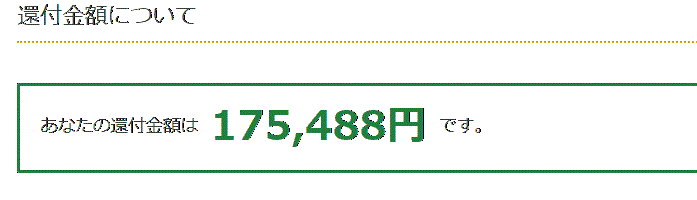
一見多いように見えますが、これは令和4年分で終了する総合課税により申告した配当控除が大部分を占めています。
令和5年からは住民税と連動するので、制度は残っていても総合課税での申告メリットはありません。
総合課税で還付されたことで、課税所得額に配当所得額が加わります。
住民税は、課税所得額を元に算出されます。
国民健康保険料と介護保険料は、住民税と連動するため、むしろ還付額よりも高く払い込みをしなければならなくなる恐れがあります。
令和5年分からは、配当所得は源泉徴収で、課税所得に加えない方が無難です。
わずか2年だけのバブルでした。
管理人の場合は、制度改正のおかげで令和4年5月からiDeCoを掛けることでき、申告できたことがとてもうれしいです!

これだけで、27,600円が還付される計算です。
7 我が家の令和4年確定申告 妻編
続いて妻の分です。
妻もiDeCoにようやく加入させました。
また、家族の医療費控除を行いました。
もちろん手続きは管理人がすべて代行です。

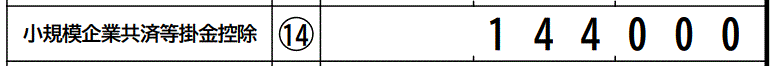
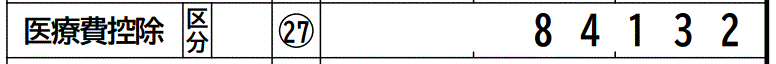
これにふるさと納税寄付金を出しての還付金予定額です。
ふるさと納税の申し込みから確定申告のための証明書の確認まですべて管理人のお仕事です。

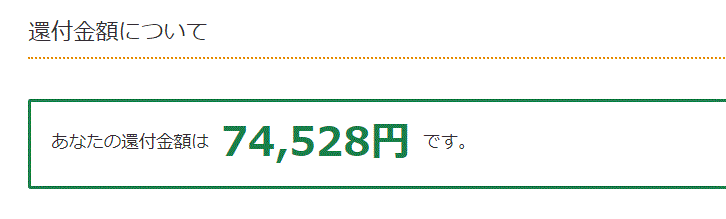


2人で約25万円もの臨時収入は、本当に助かります。
なお、ふるさと納税寄付額の住民税分の還付金は、6月以降の住民税から毎月引かれるので、なんとなく得したという感じにはならないかと思いますが、しょうがありません。
8 まとめ
確定申告は面倒です。
ふるさと納税は、寄附しただけでは還付金は戻ってきません。

対象自治体を選び返礼品が届くと、1週間‐数週間待って、寄付金納税証明書が届きます。
これをしっかり確定申告書作成等コーナーのサイトで入力し、原本を添付しなければなりません。(税務署窓口手続きの場合)
また、医療費控除も10月以降は領収書をしっかりと取っておかなければなりません。
寄付金納税証明書も医療費通知書や領収書もしっかりとコピーを取って、5年間保管しておかなければなりません。
iDeCoも11月頃自宅に証明はがきが届くのでしっかりと保管しておきます。
年末調整を行う場合も、生命保険料支払い領収書や地震保険料支払い領収書の添付が必要です。
お金を取り戻すためには、証明する書類を確定申告前にしっかりと保管しておかなければなりません。

確定申告が面倒と考えると何も進みません。
面倒だからこそ、ハードルを乗り越えないと還付はないと考える方が自然です。
確定申告で、少しでも支払いすぎた重税を取り戻してみてはいかがでしょうか?
なお、確定申告は一人一人の人生の背景が大きく左右されます。
灯りの数だけ背負っている人生があります。
確定申告が不明な場合は、国税庁相談窓口やお近くの市区町村におたずねされるか、思い切って無料税務相談の活用をおススメします。
また、還付金額が多い場合は、思い切って税理士に手続きを依頼することも選択肢です。
管理人は、確定申告還付金(予定)は2月期末に優待権利が確定する株式に投資してしまいました。

ブログと確定申告に愛と真の情報を
それではまた